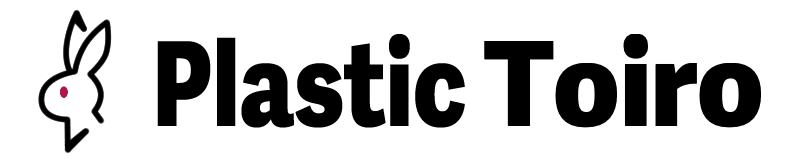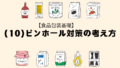ここでは、食品包装に使用される印刷方式を取り上げていきたいと思います。普段印刷するには特に気にする必要はないですが、SDGsや効率化を意識した場合には考慮の対象となってきます。また、費用やロットなどを考えたときにはハードルも簡単なものではないので、さまざまな点に熟慮は必要になってきます。
グラビア印刷
まずは、代表的な印刷としてグラビア印刷が挙げられれます。通常の食品包装のフィルムには、この方式が採用されています。
詳しくは【食品包装基礎】(5)製版と印刷で説明していますが、繊細で美麗な表現ができることが特徴です。凹版印刷の一種で、金属に溝を彫り、その中にインクを付着させ、フィルムに転写していきます。写真のようなリアルな画像を印刷するには最低5色の版が必要になり、その版は金属をベースに作られていて高価なため、初期費用が比較的高めになります。その分、高速で印刷することが可能で、1袋あたりの単価を抑えることができます。
環境面から見ると、版は一度作ると表示内容が変わらない限り、数十回単位で使い回すことができるため経済的ですが、毎回洗浄が必要で、多くは有機溶剤が使用されています。また使わなくなった版は再加工され別の商品に利用されます。環境にとっては、良い点・悪い点が混ざった状況ですが、取り組みも進められており、今後は環境に配慮した対策が期待されます。
グラビア印刷などの印刷には版と呼ばれる金属のブロックが使われますが、この版は約1年ほど使用しなかったら錆などで劣化が進むため、どのメーカーでも落版と呼ばれる処理をして、廃棄、あるいは再利用という形で別の製品に作り直されます。その前に、再度印刷を実施すればその期間はリセットされて、またそこから1年保管されます。落版は、印刷を依頼している食品会社などの都合は関係なく(連絡はあります)処理されてしまいますので、印刷を依頼する側からすると、あまり動かない製品を抱えておくことで、こういったリスクが伴います。
ここで気になるのが、版は依頼側の費用で作成して印刷をお願いしているのだから、残しておくように依頼することもできるのではということですが、版代というものは実は版を作成する手数料であり、所有権ではないということです。メーカーが所有し、品質を保ち、次の印刷まで保管しているということになります。そのため、1年以上動かない商品での印刷は、毎回版代がかかるようになってくるので、印刷方式を変えるなど別の方法も検討しなくてはなりません。
フレキソ印刷
フレキソ印刷は、グラビア印刷と反対で、凸版印刷を利用した印刷方式になります。ゴムや樹脂のような柔らかい素材で版を作成し、その出っ張った方にインクを乗せて印刷をする方式です。ハンコみたいなイメージで良いと思います。ダンボールではこの方式が多く使用されていますが、日本国内のフィルムの印刷では、まだまだ使用率からいくと少数派になります。
グラビア印刷との大きな違いは、インクに主に水性インクを使用していることで、環境負荷がグラビア印刷に比べて非常に小さいということです。水性インクはグラビア印刷で使用されるインクより濃度が薄いため、非常に管理しやすく、洗浄などにかかるコストも抑えることができます。ではなぜグラビア印刷よりも普及していないかというと、一つの大きな理由は、今までのフレキソ印刷はグラビア印刷よりも出来上がりの美麗さが悪いとされていたからです。店頭で販売されるまでの美粧性としても、やはり完成度は上げておきたい日本人独特の美に対する気質には、受け入れられにくかったのでしょうね。しかし現在では、グラビア印刷にひけを取らない出来栄えになっているので、環境保護に対する意識が強くなってきた現代では、グラビア印刷よりも有利性は高いと言えます。
デジタル印刷
近年注目されている印刷方式の一つに、このデジタル印刷があります。他の印刷方式と一番の違いは版を作らず、直接デジタルデータを印刷物に転写できることです。版を作らないことでの利点は、以下のようなものが挙げられます。
・落版がない。
・毎回、あるいは面ごとにデザインを変更できる。
・環境負荷が小さい。
版がないので、もちろん落版がありません。版の再製造を心配しなくて良いので、動きの少ない商品にも向いています。また、デジタルデータから印刷をかけるので、印刷の度にデザインも変更しやすいです。また、1ロットすべての袋のデザインを変更しようと思えば可能です。ペットボトルに名前を入れるキャンペーンなどは、このデジタル印刷の技術を利用したものです。また版がないので印刷後に版の洗浄の必要がないため、環境負荷も少ないです。
デメリットも、もちろんあります。まだまだ普及段階の技術のため、1枚あたりのコストがどうしても高くなります。通常の袋の2〜3倍の価格になってしまいます。では、なぜ導入するところがあるかというと、一つは小ロット対応ができるということです。デジタル印刷では通常の4000m以下の数量で対応してくれるところが多いため、初回の枚数を落とせます。シリーズもので3種類のアイテムで商品を出したいが、売れるかどうか分からないので枚数を落として、在庫になるリスクを減らしたいというときには向いています。また、1回の印刷で複数のデザインを入れられるため、1ロット印刷したとしても1デザインあたりの枚数は落とせるといったメリットもあります。そこで、トータルコストで考えたときに、版代がかからないため、グラビア印刷でかかっていた版代を1枚あたりの袋単価に回せます。
まとめ
今回は3つの印刷方式を紹介しました。それぞれ目的に応じて発展してきたため、明確に目指すところが違うと思います。印刷をしなければならない商品の目的を見極めて、適切な印刷方式を選択するようにしていきたいですね。