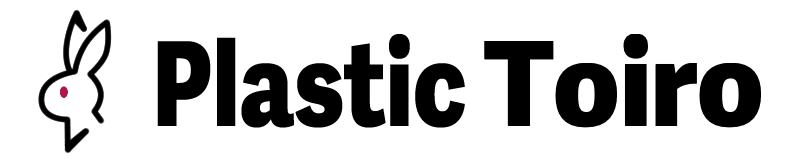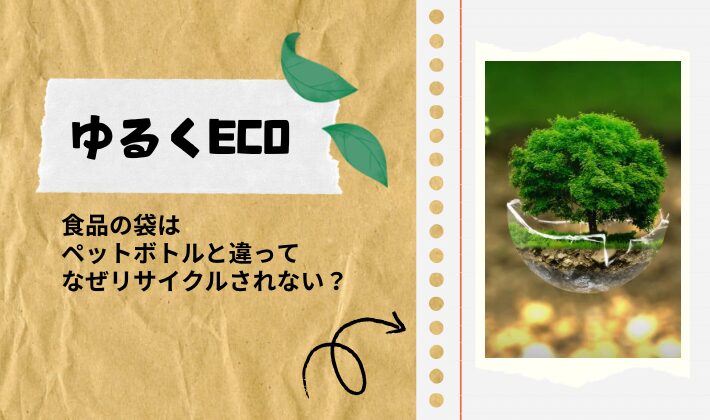スーパーなどに、ペットボトルやトレーのリサイクルボックスが設置されて、日々家庭で出るプラスチックごみの回収に協力されている方も多いと思います。そのなかで、こっちのトレーは回収されるけど、こっちのトレーは回収していないなんてことがありますよね。このリサイクルの不思議を、包装フィルム視点で、ゆるく考えたいと思います。
リサイクルマーク
プラスチック製品には下図のような「プラマーク」というロゴが製品のどこかに必ず記載されていることはご存知だと思います。このマークは、資源有効利用促進法に基づいて指定された容器包装に表示することが義務付けられています。「PET」「紙」「アルミ」なども識別マークのひとつですね。

識別マークがつけられるのは、プラスチックは外から見ただけでは、どんな素材で出来ているか見分けにくいものも多く、ゴミの分別がしやすいようにと考えられたものです。このマークがあるおかげで、どうリサイクルしないといけないか分かるようになっています。
しかし、スーパーなどに設けられている回収ボックスには、同じプラマークがついていても回収してもらえない袋やトレーがたくさんあります。これらの回収されないプラスチック製品は、通常のゴミと一緒に廃棄されて、焼却されたり埋め立てられたりしています。せっかく同じようにリサイクマークが付けられているのに、なんだか残念な扱いですよね。この理由は、包装フィルムを作る過程を知ることで見えてきます。
回収されない理由
例えば、レトルト商品や冷凍食品で使われている袋の多くは、包装フィルムというプラスチックで作られています。この包装フィルムは、見た目1枚のフィルムを袋状に加工しているように見えますが、実は複数のプラスチックフィルムを接着剤で貼り合わせた複合素材となっています。なぜ複数のフィルムにするかというと、中に包む製品を守るために必要な機能(光を通しにくい、酸素を通しにくいなど)が必要だったり、美粧性を出すための印刷を施したいといった理由があります。それを1枚のフィルムで全て補うには、まだまだハードルが多い状況です。
このことをもっと詳しく説明もしているので、興味ある方は下記のページを見てください。
実は、この複数のフィルムを貼り合わせていることが、リサイクルに制限がある原因の一つになっています。ペットボトルのように単体で透明であれば、いっきに溶かしてしまえば再生に使える状態まで持っていくことも容易ですが、複数のフィルムではそれぞれ違う組成の違う原料で出来ているため、まとめて溶かしても混ざってしまい、元のプラスチックには戻りません。また印刷を施していると、色も汚れてしまいます。これをそれぞれの組成ごとのプラスチックに戻そうと思うと、各フィルムに分解して作り直すという過程が必要になってきます。こういった理由もあり、回収されないのです。
今後期待されること
企業や大学、その他研究機関では、この回収問題について日々研究が続けられています。環境負荷を減らしていくために植物由来のフィルムを考えたり、モノマテリアルといって、さきほど述べたような複数の組成の違う原料を使わず、単一の組成の原料で同じような機能を持てるフィルムを考えたりと、日々努力しています。また、貼り合わせたフィルムを剥がして分けていく技術も出来ていているようですよ。
これらが次第に市場でも使われて、良いものだと認知されてくれば、費用も抑えて使えるようになり、大企業だけでなく中小企業でも扱うことができるようになります。そうなれば、リサイクルができるプラスチックも増えてくる、と期待出来ます。
将来、環境保護の一端に結びついてくるといいですね。