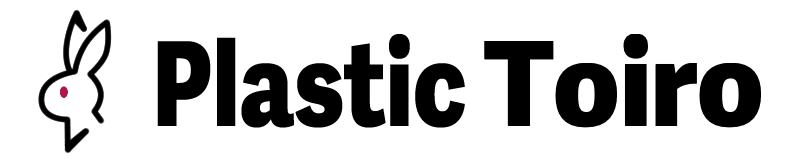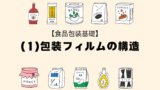食品包装の袋の完成までには、多くの工程があります。ここでは全体の流れがイメージできる程度の簡潔な内容で説明していきたいと思います。
包装の製造工程
食品包装の流れを箇条書きにすると、下記のようなものになります。
- 版下の作成
- 製版
- 印刷
- ラミネート
- エージング
- スリット・製袋
簡潔に記載していますが、これ以外にも各工程に検品が入ったり、梱包が入ったり、いろいろな工程を得て、各食品メーカーに納品されます。
それでは、それぞれの工程について以降で説明していきたいと思います。
版下の作成
「版下」とは袋に印刷をして、美粧性をもたせたり、一括表示を表示する場合に必要な、下書きになります。
加工食品などの食品は、食品表示法等でその製品に関する情報(一括表示や栄養成分表示)を食品包装に記載することが義務付けられています。その表示方法として使われているのが、食品包装の袋に直に印刷を施す方法です。この印刷の元になる原画が「版下」になります。版下は、お店で並んでいる食品包装と同じイメージになるように作成されるので、どこにどういう文字や色をつけていくかを人が見て分かりやすくなっています。
この版下を元に、次の工程の「製版」が進められていきます。
製版
「製版」とはフィルムに印刷をするための判子のようなものを作る工程で、先程の版下を元に円柱状の金属(鉄やアルミの芯にメッキを施したもの)に印刷したい内容を彫り込んでいきます。この掘り込まれた円柱の金属を「版」と言います。
掘り込む内容は、版下を元にシアン、マゼンダ、イエロー、墨(黒)、白などに色分解がされて、それぞれ1本づつ作られます。単調な2〜3色の色だけで出来上がっている版下の場合は、特色と言ってそれぞれ対応した専用の版を作ります。しかし、写真などのフルカラーで表現する場合は、墨、白以外の色は、シアン、マゼンダ、イエローの3本の版で表現をしていきます。そのため、フルカラーの版下には最低5色分の版(5版と言います)が作られます。これ以外に、さらに特別な色合いを出したい場合は版を追加して、特色を増やして色を表現します。
3色でほぼ色が再現できる理由は、フィルムにインクが付着する際に網点状になるように版を彫っているので、シアン、マゼンダ、イエローのそれぞれのドット(点)の数や密着度の差から、遠くから見るといろいろな色がついているように見えるからです。
印刷
製版ができると、その版に対応した色のインクをつけて、フィルムに印刷をしてきます。印刷方法は使われる機械や環境によって様々な方法がありますが、今回はグラビア印刷を例に上げていきます。
グラビア印刷では、先程の項目で作った版を使って印刷をしていきます。版はシアン、マゼンダ、イエローなど必要なインクが入ったタンクの上に、それぞれ備え付けられて回転します。この版は凹状に削られており、凹部にインクを溜めていきます。溜まったインクは回転しながら印刷したいフィルムに押し付けられ、着色されます。
インクは袋の表面からこすっても消えないように、基本的にはフィルムの裏側に印刷されていきます。一番濃い墨が先に塗られ、続けてシアン、マゼンダ、イエロー、白と徐々に薄い色が塗られるようインクのタンクが並べられます。また特色はその種類によって、どこの間に入るか決まってきます。水彩画などは薄い色から塗って、濃い色ではみ出ているところを上塗りしてきれいなラインに仕上げていきますが、フィルムは裏から塗るので「水彩画の反対の順で塗っていくと、濃い色に薄い色がはみ出ても色が出にくいから濃い順に塗る」とイメージすると良いと思います。
ラミネート
食品包装は様々な機能を持ったフィルムを貼り合わせた複合素材で出来ています。ラミネートとは、その様々な機能を持ったフィルム同士を貼り合わせ、1枚の高機能フィルムに仕立てる工程になります。
ラミネートの方法としては、「ドライラミネート」と「押出しラミネート」などがあります。それぞれの工法と特徴は以下のようになります。
| ドライラミネート | 押出しラミネート | |
| 工法 | 接着剤を使用して基材となるフィルム同士を貼り合わせる。 | 高温で溶かした樹脂を基材となるフィルムに数ミクロンという薄さで押し出して貼り合わせる。 |
| 特徴 | ・全ての基材を貼り合わせられる。 ・複合機能を多く持たせやすい。 ・透明性が高い。 ・強度がある、コシがある。 | ・接着剤が不要。 ・コストが比較的安価。 ・加工速度が早い。 ・引き裂き性に強く、柔らかい。 |
エージング
貼り合わせが終わったフィルムを、品質に影響が出ない一定の温度下で保管し、接着強度を安定させる工程です。1日〜3、4日の間エージングを続けることで、貼り合わせたフィルムに強度が出て、1枚のフィルムとして出来上がります。温度や時間はフィルムの構成により様々です。また、この時間を作ることで、フィルムから出る接着剤の臭いを落ち着かせることが出来ます。
エージング時間を短くすると、フィルム同士が完全に接着されない事があるため、時短されることはありません。接着が悪いと、後々製品として使われていく間に、自然と接着面が剥がれる「デラミ」が発生したりします。そのため、とても重要な工程となっています。
スリット・製袋
スリット・製袋では、エージングが終わったフィルムをカット・シールしていき、1枚の袋に完成させていきます。フィルムの状態で納品される場合は、指定サイズにスリット(切り取り)して、紙管に巻き取っていきます。
機械を通されたフィルムは袋の表裏が重なるように折られて、指定された袋の形状にシールされます。その時、チャックが必要なときはチャックを付けたり、袋に底を付けたいとき(スタンドパックの袋にするとき)は底を一緒にシールするなど、機械のライン内で様々な機能を同時につけていきます。そして、シールされたフィルムはノッチ(切り口)やフック穴などが付けられ、袋の形状へと最終的にカットされます。これで1枚の袋としての完成となります。
その後、検品、箱詰めなどを経て、発注先の食品メーカーなどに納品されます。
以上が、食品包装ができるまでの、おおまかな流れとなります。近年は様々な機能を持った袋も出てきているので、上記の流れで全てが完結しないものもありますが、基本的を押さえておくことで、応用的な方法も理解が進むと思います。