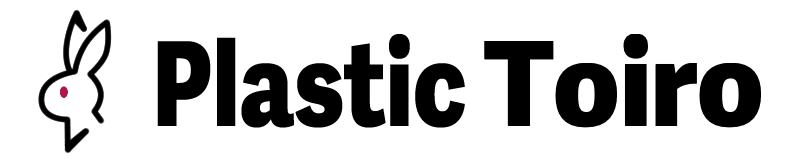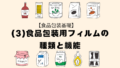冷蔵庫に残り物を入れるときなどに使用するラップは、色々なメーカーから出ていますが、お皿にピタッと付くものがあったり付かなかったり、柔らかかったり硬かったり、様々な品質のものがあります。これらの違いはどこから来るのか?今回はそこを、ゆるく掘り下げていこうと思います。
食品用ラップフィルムの種類
食品用ラップフィルムには、様々な材質が使用されています。材質にはそれぞれ機能に特徴があり、その違いを知ると、どういったものに使うと最大限機能を活用できるかが分かってきます。家庭で使用する代表的な3種類は、以下のような特徴があります。
ポリ塩化ビニリデン(PVDC)
酸素や臭い、水分を通しにくいため、肉・魚の保存や、臭いのきついもの(キムチやチーズ)などの保存に向いている。また、熱にも強いため、電子レンジで温める場合にも便利。
ポリ塩化ビニル(PVC)
伸縮性、耐久性、密着性に優れているため、スーパーのお肉や出前のラーメンなど、業務用で使用される。ポリ塩化ビニリデンに比べて酸素や水分を通しやすいので、冷蔵庫での保管用には向かない。
ポリエチレン(PE)
水分は通しにくいが、酸素は通しやすいため、ある程度の空気の出入りが必要な野菜や果物などの保管に向いている。密着性は悪いため、フタ代わりにお皿に巻き付けても、うまくつかない。価格は他に比べて安い。
ラップフィルムの見分け方
先ほど上げたように、ラップフィルムでも様々な特徴を持っていて、向き不向きがあることが分かると思います。では、どこでそれを見分けるのか?いちばん簡単な方法は、ラップが入っているケースの裏側にある一括表示の「原材料名」という項目に、ポリ塩化ビニリデン、ポリ塩化ビニル、ポリエチレンと記載があるので、ここで確認すれば識別できます。
再利用して少しだけ環境にやさしく
ラップフィルムは基本プラスチック製品のため、今のSDGsを目指す環境下では、なかなかの嫌われ者の部類に入ります。でも使わないわけにはいかない。そこで1回使って捨てるにはもったいないので、使用後に2次利用で掃除用のスポンジや埃よけなどに使われる方も多いのではないでしょうか?
我が家では、保存用として使ったあとのラップは、食事が終わったあとの皿についたドレッシングの残りや、こびり付きなどのカス取りに使っています。あと、カレーなどの鍋に残った残骸を取ったりしています(フッ素樹脂加工には使ったら駄目ですよ)。この毎日の食事でお皿に残るカスを流しに流さないことで、環境的にメリットが少しだけあります。
各ご家庭には、特に一軒家を持っている方は分かると思うのですが、排水桝(はいすいます)というものがあります。敷地内にある、塩ビなどの小さな蓋付きのマンホールです。ここには、台所などから流れてきた水が通るのですが、油や固形物を下水に流さないようにするために設けられています。ここは定期的に掃除しないと、排水管が詰まったり、そのまま油などが排水されていってしまいます。かなりのペースで油や固形物が貯まるので、年に何度か掃除をしないといけないのですが、先程のラップの掃除を毎日食器洗浄の前にしておくと、小さなゴミまで流れることがほとんどなくなるので、かなり貯まる頻度が改善されます。頻度が減るということは、水もできるだけ汚さないように流れているということなので、間接的ではありますが、環境維持に役立っているのではないかと思います。
一人では大きな環境改善は難しいですが、自分たちのできる範囲で少しずつ考えることで、環境にとって良い方向に進めていると思いたいですね。